この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。

「事故あり係数とは?適用期間っていつまでなの?」
特に事故を起こして保険を使用した人は、保険料に大きく影響を及ぼしますので、この「事故あり係数」の事が気になるのではないでしょうか?
そこで今回は、2012年4月に改定されたノンフリート等級制度において導入されている「事故あり係数」やその適用期間、保険料への影響などについて紹介させて頂きます。
また、事故あり係数を回避する方法を考えている方もいると思いますので、その点も可能か否かも含めて、併せて紹介させて頂きます!
それではまず、「事故あり係数・適用期間とは?」という基本事項から見ていきましょう!
事故あり係数とは?適用期間はいつまで?

事故あり係数とは、ノンフリート等級制度における「無事故等級」と「事故有等級」の2つの割引率のうち、低い割引率(保険料が高くなる)の方を指します。
事故を起こして自動車保険を使用した場合に翌年度から適用されます。
そして、この事故あり係数が適用される期間の事を「事故あり係数適用期間」と言います。
なお、事故を起こした事が無い人の保険証券にも「事故あり係数適用期間:0年」と記載されています。
じゃあ、どの程度の期間「事故有係数」が適用されるのか?
というと、それは起こした事故が「何等級のダウン事故に該当するか?」に依存します。
つまり、3等級ダウン事故であれば翌年度から3年間は「事故あり係数」が適用されます。1等級ダウン事故なら1年間適用されます。
- 「3等級ダウン事故」なら、次年度の契約から3年間
- 「1等級ダウン事故」なら、次年度の契約から1年間
そして、事故有り係数適用期間は、翌年度以降無事故で過ごせば、1年間ずつ適用期間が短縮されていきます。
つまり、適用される期間を無事故で過ごせば、通常の「無事故等級」へと戻る事が出来ます。
■3等級ダウン事故の場合のイメージ
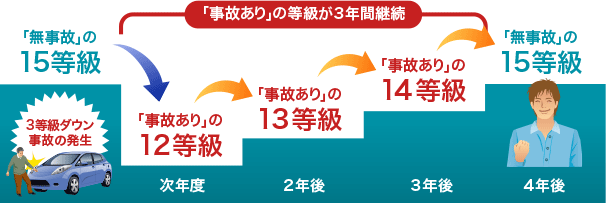 (出典:保険を使った事故を起こした場合、次年度の等級が下がります | ソニー損保)
(出典:保険を使った事故を起こした場合、次年度の等級が下がります | ソニー損保)
■1等級ダウン事故の場合のイメージ
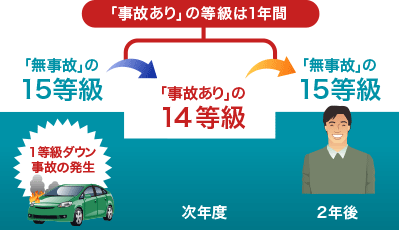 (出典:「事故あり」の等級の継続期間 | ソニー損保)
(出典:「事故あり」の等級の継続期間 | ソニー損保)
1等級ダウンなら1年が、事故あり係数適用期間として加算されるということです。ただし、事故あり係数適用期間は最大6年です。
それ以上は何回事故を起こしたとしても増えません。
1年間事故がない場合は、事故あり係数適用期間が1年減算し、下がった等級分の年数が新たに加算されます。
事故を何回も起こすのは問題ですが、その度に事故あり係数適用期間を無限に増加させていくと、いつまで経っても無事故等級に戻れない事への配慮でしょう。
同一年度に2回の事故を起こした場合
事故あり係数適用期間は「年度単位」ではなく「事故単位」で加算されるので、同一年度に2回事故を起こしたら2回分のペナルティーが発生します。
たとえば、3等級ダウン事故を同一年度に2回起こしてしまえば、合計6年間は「事故有り係数」が適用されます。
2年連続で事故を起こした場合
2年連続で事故を起こした場合の事故あり係数適用期間は、以下のように計算されます。
「1回目の事故で適用される期間」-1年+「2回目の事故で適用される期間」
たとえ2年連続で事故を起こしたとしても、適用期間が1年ずつ短縮されていくルールに変わりはありません。
ただ2回目の事故に関する適用期間が加算されるので注意が必要です。
2年連続の事故に関する事故あり係数適用期間については、イメージ図を見た方が分かりやすいと思うので、以下の図(2年連続3等級ダウン事故を起こした場合)を参考にしてください。
 (出典:2年連続で事故をした場合の事故あり係数適用期間|ソニー損保)
(出典:2年連続で事故をした場合の事故あり係数適用期間|ソニー損保)
【参考】事故あり係数適用期間・事故有等級が導入された経緯
以前の等級制度では「事故を起こして等級が下がったドライバー」と「事故を起こさずに等級が上がったドライバー」の等級が同じだった場合、両者には同一の割引率が適用されていました。
具体例を挙げると、「15等級だった者が事故を起こして12等級になった場合」と「11等級だった者が事故を起こさずに12等級になった場合」とで適用される割引率に違いが無かったんです。

事故を起こしていない人の中には、旧制度に不公平感を抱く人も少なくなかったんです。
無事故の人が事故を起こした人よりも保険料などで優遇されるべきだ!と考えるのは当然ですよね。
また、「事故を起こして等級がダウンしたドライバー」と「事故を起こさずに等級が上がったドライバー」とを比較すると「事故を起こして等級が下がったドライバー」の方が今後も事故を起こす確率は高いという統計学的な結果が出ていました。
そこで、事故を起こしたドライバーには「事故あり係数」を適用し、その期間中は「事故有等級」に基いて割引率を決定しましょう、という事になったのです。
ただ、旧ノンフリート等級制度でも、事故を起こすと翌年度には等級が下がり、それに応じて保険料が高くなっていましたから、ペナルティーが全く課されていなかったわけではありません。
事故あり等級と無事故等級で保険料にどれくらいの違いが出る?
現在のノンフリート等級制度の割増引率表は以下のようになっています。
下記表の「+」は割増を、「△」は割引を表しています。
| 等級 | 無事故 | 事故有 |
|---|---|---|
| 1等級 | +108% | +108% |
| 2等級 | +63% | +63% |
| 3等級 | +38% | +38% |
| 4等級 | +7% | +7% |
| 5等級 | △2% | △2% |
| 6等級(F) *1 | △13% | △13% |
| 7等級(F) *1 | △27% | △14% |
| 8等級 | △38% | △15% |
| 9等級 | △44% | △18% |
| 10等級 | △46% | △19% |
| 11等級 | △48% | △20% |
| 12等級 | △50% | △22% |
| 13等級 | △51% | △24% |
| 14等級 | △52% | △25% |
| 15等級 | △53% | △28% |
| 16等級 | △54% | △32% |
| 17等級 | △55% | △44% |
| 18等級 | △56% | △46% |
| 19等級 | △57% | △50% |
| 20等級 | △63% | △51% |
*1 新規契約者には基本的に事故有り係数が適用されないので、6・7等級には継続契約者の「F」のみを記載しています(参考:ノンフリート等級のアルファベットの意味)。
これを見ると、両者の割引率に差が無いのは6等級以下の場合だけで、それ以上になると「事故有」の場合と「無事故」の場合で割引率に大きな差が発生している事が分かります。
例えば、12等級の場合では、「無事故等級」の人は50%もの割引が受けられるのに、「事故有等級」の人は22%の割引しか受けられません。
仮に割引前保険料が10万円だった場合には、両者で「2.8万円もの保険料の差」が発生することになります。
事故有等級制度の導入により、保険金を請求すると翌年度からの保険料がかなり上がる事が予想されます。
保険を利用するかしないかの判断は慎重に行って下さい。
事故あり係数を回避する方法はある?
上記のように、事故あり係数が適用されれば翌年度以降の保険料が高くなってしまいます。
事故有等級をなんとか回避したいところですよね。
そこで、以下では事故あり係数を回避できるかどうかについて紹介します。
他社へ乗り換えても「事故あり係数」は引き継がれる?

保険会社を変更すれば事故有り等級は引き継がれないのでは?
と考える人がいるようですが、保険会社間で等級情報などが共有されているので、その考えは通用しません。
この情報共有制度を「自動車保険契約確認のための情報交換制度」と言います。
この制度には損保だけでなく、共済も参加しているので、どの自動車保険・共済に乗り換えても事故あり等級が引き継がれます。
ただし、「事故あり係数」の回避が目的ではなく、保険料を安くする事が目的であるならば、保険会社の乗り換えは無駄ではありません!
現在契約中の自動車保険よりも、自身の状況の変化により、保険料が安い保険会社が有るかもしれません。
もしかしたら、もっと安くなるかも!?と思った方には「自動車保険一括見積もり」がオススメです。
各社に一つずつ問い合わせするのも、大変な作業です。またその為に、返信したり、電話に答えたりと労力もかかるでしょう。そのような手間を極力少なくする為に、一括見積もりで自身のニーズを絞り、対応する事が効率的に対応できるので、オススメです。
一度、チェックしてみるのをオススメします。
解約して新規加入しても「事故あり係数」は引き継がれるのか?
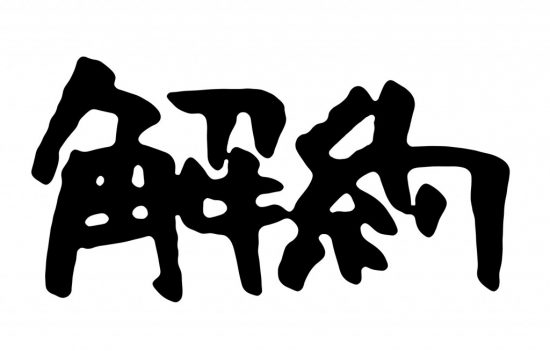
次に思いつく方法が「現契約を解約して新規で加入し直す方法」です。
事故有り等級をリセットしてしまおう、という目論見ですね。しかし、この方法でも事故あり係数が引き継がれてしまいます。
というのも、事故有等級や1等級~5等級などのデメリット等級は、一定期間が経過しない限り引き継がれるルールになっているからです。
| メリット等級(6~20等級) | 前契約の満期日の翌日から7日以内 |
|---|---|
| デメリット等級(1~5等級) | 前契約の満期日の翌日から13ヵ月以内 |
保険金の貰い逃げは許さない、といったルールですね。
その一定期間というのが「13ヶ月」です。
解約日又は満期日から13ヶ月が経過しなければ、事故有り等級はリセットされません。
また、事故歴や等級を隠して自動車保険を新規契約することは「告知義務違反」にあたります。
逆に言えば、一旦自動車保険を解約して13ヶ月が経過すれば、等級情報は抹消されますので「事故有り係数適用期間」も無くなります。
この場合、等級は6等級からスタートになります。
なお、中断証明書を取得すれば現在の等級を引き継げますが、事故有係数適用期間がリセットされることはないので注意してください。13ヶ月が経過していたとしてもです。
事故を起こした時点であまり等級が高くなく、それほど車も使っていなかったという人であれば、一旦自動車保険を解約して13ヶ月待ってから再加入した方が保険料が安くなる可能性も有るので、そこはケースバイケースですね。
注:解約して13ヶ月間が経過するまで待つ場合、その間は当然ながら任意保険未加入の状態となります。
法的に公道での走行が制限されているわけではありませんが、事故を起こした時の事を考えると、事故有り係数のリセット待機中の運転はおすすめ出来ません。
【事前の策】長期契約なら影響を最小限に抑えられる
3年や5年などの長期契約は複数年契約とも呼ばれ、契約時点の条件でその後の契約期間の保険料が算出されます。
つまり、契約期間中に事故を起こしたとしても事故有り係数による保険料の値上げの影響を回避する事ができます。
長期契約の最大のメリットです。
事故有り係数の適用を回避したいのであれば、長期契約で自動車保険に加入しておく、という手もアリですね。

ただし、これはあくまで事前の対策です。
事故後に長期契約に変更しても意味は無いので注意してください。
また、長期契約最終年に事故を起こした場合は、翌年度の更新から事故有り係数が適用されるので、1年契約と同様の結果になります。
この点も併せて注意してくださいね。
長期契約の詳細は下記記事をご覧いただきたいのですが、もう1つ注意点を挙げると、長期契約を結べるのは代理店型のみなので、通常時の保険料が高くなってしまいます。
メリットとデメリットを見極めて、契約の判断を行ってくださいね。
まとめ
今回は「事故あり係数」及びその「適用期間」について紹介しました。
無事故等級の場合よりも低い割引率が適用される「事故あり係数」。
誰もが翌年度の保険料を見て「高い!?」と感じるはずです。しかし、今回紹介したように、事故あり係数の適用を回避する方法は有りません。
事故を起こしてしまった以上、保険料の値上げを甘んじて受けるしかないんです。ただ、簡単に値上げを受け入れるのではなく、契約内容の見直しによる保険料の節約は必ず行いましょう。
付帯している特約が本当に必要なのか、これを機に考えてみてくださいね。






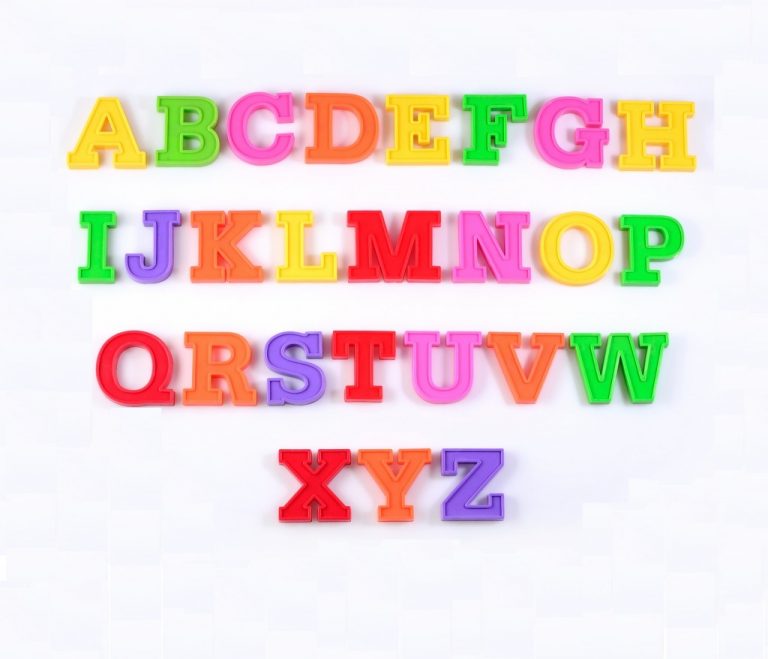

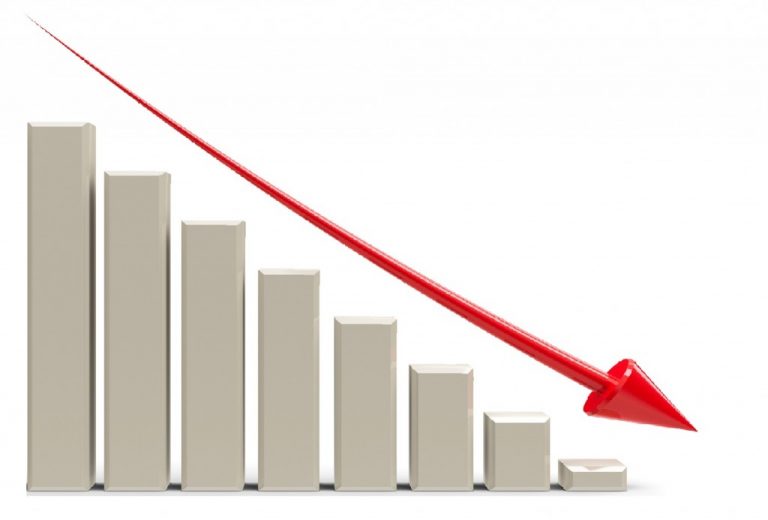






コメント
この記事へのコメントはありません。