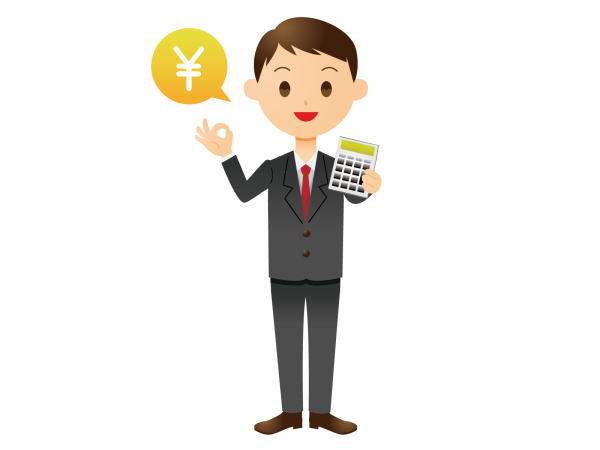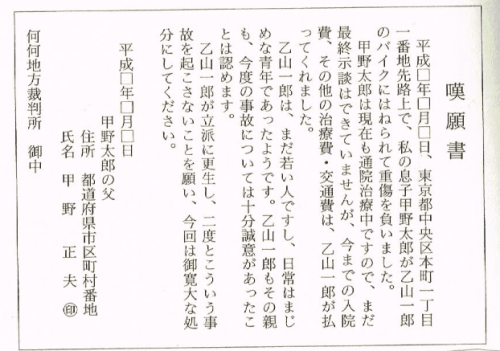この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
交通事故に遭遇し当事者の間で示談がいったん成立した場合、後になってこれを取り消すことはできるでしょうか?交通事故に遭遇したとき被害者は精神的に一杯いっぱいになっていることもあり、示談が成立するまでに間違った判断をしてしまうことなどもよくあります。
例えば、示談の相場調査を忘れていて示談が成立してからもっと高く貰える事に気付くなんてことが該当します。。示談は一種の契約なので成立した後は一方的に取り消すことはできません。この例の場合、被害者が慎重になっていれば避けられたことなので原則取り消す事は出来ないのです。
そこで、色々なパターンにわけて成立した示談を取り消すことが出来るかについてみてみましょう。
[myphp file=’kiji-top’]
①書面を作成していなかった場合
示談(契約)は話し合いで成立するものであって書類を作ることは基本的に成立の要件ではありません。しかし、話し合いが成立したときに示談書を作成しておかないと本当にそれで契約が成立したか否かを後々証明することが難しくなってしまいます。
特に、被害者側は少しでも多く示談金が欲しいと思うでしょうし加害者側は少しでも示談金を少なくしたいと考えているので示談書がないと後日お互い自分に有利な金額を主張することも考えられます。後になって「話し合いの時点そんな契約は成立していなかった!」と主張されてしまうと、もはやお互いに対抗する術はなくなってしまうわけです。これが口約束の怖いところですね。
示談が成立したと言い切るのはやはり書面を作ってお互いが署名・押印した時点と考える方がよいですね。
②示談の内容に錯誤があった場合
錯誤という言葉は民法上の用語で、要は勘違いという意味です。意思表示をする過程で重要な点に勘違いがあった場合にはその意思表示は無効となるというのが民法での取り扱いです。
ただ、ここで重要になってくるのがその錯誤が「量的な錯誤」か「質的な錯誤」かどっちなんだという問題です。
記事冒頭で書いた「相場を調べていなかった」というケースはどうなるでしょうか?これは相場=金額の問題ですので質的な問題ではなく量的な問題です。量的な勘違いの場合には意思表示は無効とならないのが通常の考え方です。つまり質的な内容に重要な勘違いがあった場合に無効となることになります。
質的な勘違いとは例えば3回病院に通院して痛みも治まっておりレントゲンなどでも異常なしと判断されたので示談を成立させたものの、後になって痛みが再発し入院や通院が改めて必要になった場合などです。
このような場合、後日の入院などが元々分かっていれば示談はしなかったと認められるので、最初の示談成立の過程に錯誤があると判断できます。従って示談が無効と言えるのです。
③代理人の無権代理の場合
これは被害者が他人に頼んで示談交渉をしていて、その他人が勝手に示談を成立させてしまった場合の話です。示談交渉は依頼しても示談を成立させるところまではお願いしていない場合、無権代理(代理人の権限を越えている)の問題が発生することになります。
こういう問題が起きない様に、委任状をしっかりと作成し代理人の権限についてどこまで任せるのか(示談を交渉するだけなのか、示談の成立までする権限を与えるのか)を明確にしておく必要があります。
権限を委譲していないのに勝手に示談を成立されてしまった場合は無権代理となるので基本的には取り消すことができるのですが、以下の様に取り消せない場合もあるので注意が必要です。
例えば、示談の交渉のみを任せたつもりだったけどハンコを代理人に渡していて代理人が示談書の作成まで行ってしまった場合でかつ示談内容が相場とひどくかけ離れていない場合。
このような場合には民法でいう表見代理(外観上代理権を与えているように見える場合は代理権があるものとみなされることがある)が成立してしまい、取り消すことができなくなることがあります。
④相続人が複数で一部示談書から名前が漏れていた場合
示談成立のために示談書に被害者のサインが必要となりますが死亡事故の様に被害者が死んでいる場合は相続人が示談書にサインをすることになります。相続人は一人とは限らないので相続人が複数いる場合は原則として全員のサインが必要となります。
示談書から相続人の一部の署名が漏れていたような場合は、一般的に示談書は後で取り消すことはできず、有効なものと判断されます。名前が漏れていた事は単なるミスであって、示談を不成立とするほど重要なこととは通常は判断されないからです。