この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
交通事故で被害者・加害者間で示談をする過程で示談書を作る事になりますが、示談書の作成時・サイン時に注意すべき点について見ていきましょう。
事前に専門家に相談を!
示談書には、成立した示談の内容が全て書かれることになります。
つまり記載内容を間違えると、せっかく成立させた示談も無意味なものとなってしまう可能性が有ります。
示談を成立する前に必ず専門家に内容をチェックしてもらう事にしましょう。
その際は、交通事故に詳しい弁護士を選んだ方が良いでしょう。
当事者全員のサインが必要
示談書には被害者側・加害者側の全員がサインをする必要があります。
加害者側
加害者側でサインをする必要があるのは、基本的には交通事故発生時に自動車を運転をしていた方です。
通常であれば運転者と自動車の持ち主は同じ人なので問題ないですが、会社の自動車を運転していた様な場合に異なる事になります。
そこで、運転者と自動車の持ち主が異なる場合には両方のサインが必要となります。
被害者側
傷害事故の場合は被害者本人のサインで足りますが、死亡事故の場合は相続人のサインが必要となります。
この点については「示談の取消しは可能!?無権代理などのケース別スタディ」で説明をしているので参考にしてください。
また被害者に内縁の配偶者がいた場合には、内縁の配偶者は扶養請求権を侵害されたことによる損害賠償請求権を持つため、示談書には内縁の配偶者のサインが必要となります。
内縁の配偶者の損害賠償請求権については、内縁関係の妻に損害賠償請求権や慰謝料請求権は存在するか否か?を参考にしてください。
示談金の受け取りと示談書のサインは同時に!
示談金は示談書で「いつ」「どのように」「一括か分割か」などの支払方法を記載する必要があります。
また、被害者が示談書の内容通りに示談金を支払ってくれるのであれば問題ないですが、中には「金がない」と言って支払ってこない加害者もいます。
更に言うと、加害者の被害者への「申し訳ないという感情」も時が経てば薄れていきます。
そうなると「金が有っても」支払わない加害者も出てくるので、可能な限り示談金は示談が成立し、示談書にサインをするのと同時に受け取ることにしましょう。
示談金の分割払いには過怠約款を!
上記にあるように、示談金が成立して支払方法を示談書に書いていたとしても、その通りに支払ってこない加害者もいます。
そこで加害者が期日通りに示談金を支払をしてこなかった時のために、過怠約款として示談書に記述しておくことが重要です。
内容としては、「期日までに支払をしなかったときは、分割払いや期日の定めに関わらずに即座に全額支払う必要がある」や「期日までに支払をしなかったときは、違約金として○○円を追加で支払わなければならない」といった様なものが一般的です。
示談金の中に保険金が含まれているかの確認が必要
詳細はこちらの記事を確認して頂きたいのですが、被害者と相手方損保会社の言う「示談金」の額に齟齬が発生してしまう可能性が有ります。
通常、被害者は示談金を「総額」で考えますが、損保会社は「自賠責の支払額を引いた純額」で考えます。
このような齟齬が発生することにより、思っていたよりも示談金が少なくなってしまった!という事例が過去には有ったようですので、示談金の中身についてもしっかりと確認しておきましょう。
示談書は公正証書に!
一般的に交通事故で使われている示談書のほとんどが「私製の示談書」と呼ばれるもので、強制執行権はありません。
示談書を公正証書にしておけば加害者の財産を競売できる強制執行権が得られることになるので、被害者が示談金を支払わないときに有利に事を進めることができます。
また、「示談書にサインする前に専門家に相談をしましょう」と先ほど書きましたが、示談書を公正証書にする場合は法律の専門家である「公証人」が相談にのってくれるので是非内容を見てもらいましょう。
相談にものってくれて公正証書にもできるので一石二鳥ですね。
なお、示談書を公正証書にするときの費用や場所などについては「公正証書とは?費用や役場の場所」を参考にしてください。
専門家からのコメント

今回の内容は、示談書に関する内容でしたが、保険代理店としての実務面から補足させて頂きます。
交通事故の示談交渉において、示談書を取り交わすケースは年々減って来ていると思います。(あくまでも私の経験を踏まえての話ですが。)
その要因としては、複雑な事案や、中々折り合いがつかず暗礁に乗り上げた事案に関しては、保険会社(保険代理店)の手を離れ、弁護士に委任し、訴訟、裁判になる為と考えられます。弁護士費用特約のみ使用しても等級ダウンしない事や、訴訟へのハードルが下がっている事もあり、弁護士費用特約の保険料は年々増加しております。
もう一つ考えられるのは、示談書を取り交わすケースにおいて、示談書に双方の署名、捺印が完了してからでないと保険金が支払えない為、最終的な解決に至るまで時間が余分にかかる事を保険会社が懸念している事があります。
それでも実務において示談書を取り交わすケースは一定数あり、それは事故の加害側、被害側のいずれかがクレーマーの傾向があるケースや、示談に至るまで交渉が難航した場合があります。
事故の相手側が上記の様なケースにおいては、自分を守る為にも示談書を取り交わし、書面にて記録を残す事も有効な手段だと思います。








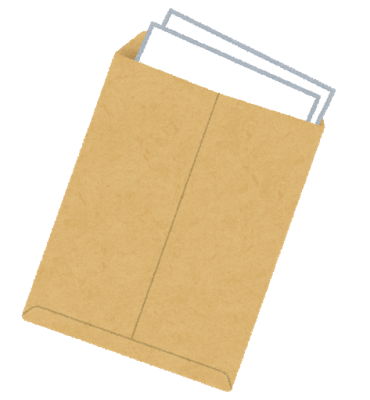




コメント
この記事へのコメントはありません。